『引き継ぎの考え方①「歴史を知ろう」』
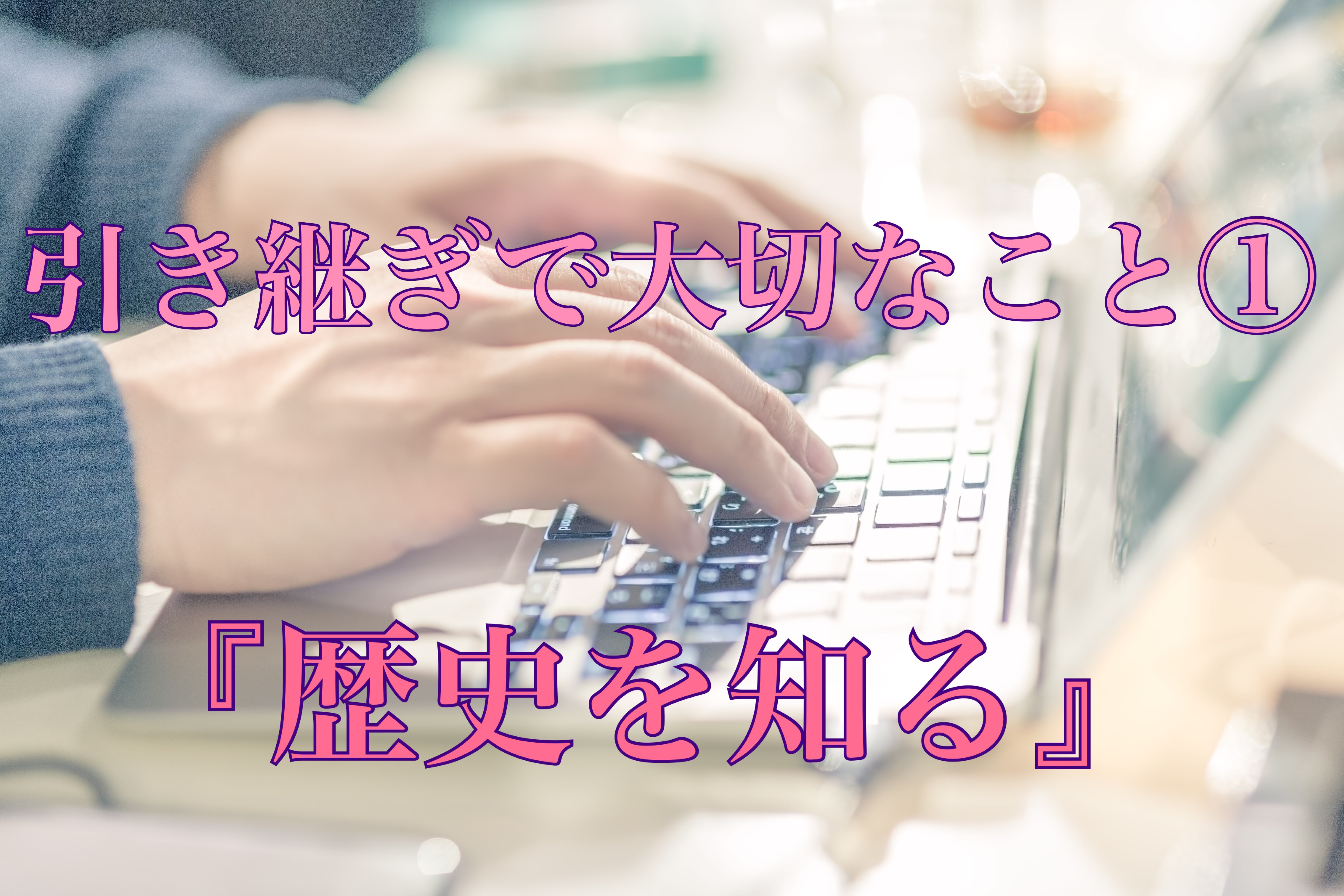
『引き継ぎの考え方①「歴史を知ろう」』
こんにちは。
新年度へ向けて、これまで担当していたお子さんの引き継ぎをしたり、また、新しく担当するお子さんの引き継ぎを受けたりする時期かと思います。
今回は引き継ぎ時の配慮点について数回に渡りお届けします。
宇佐川研では、引き継ぎをする際に、いくつかの視点をお伝えしています。
①「歴史を知ろう」
現在のお子さんの実態は、過去の指導など、積み重ねた上であります。
ぜひとも、新しく担当するお子さんについて、産まれた時からの生育歴、各療育機関などの指導内容等も含めて把握しましょう。
お子さんと、ご両親のこれまでの歴史をぜひ知って受け止めてください。
もしかしたら、担当される時に、まだまだ発達課題をたくさんあると感じることもあるかと思います。
でもそれは、これまでもっとたくさんあった課題を頑張って乗り越えてきて、やっとたどり着いた姿かもしれません。
そのような時に、その過去の頑張りを認めることなく、こんなに課題がある!などのように思ってしまったら、
お子さんも、ご両親も、懸命に努力してきた自分たちを否定されたようなお気持ちになるのではないかと思います。
長い入院歴があったとしたら、ご家族で入院も乗り越えて来られたんですね。
辛かったですね、頑張って来られましたね。
これからは一緒に乗り越えていきましょう!
と、思える支援者でないと、お子さんもご家族も、同じ方向に向くことはできないと思います。
学校であれば、過去にどのような学びをして今に至っているのか、指導やこれまでの専門家からの助言も含めて受け止めてください。
もしかしたら、誤学習もあるかもしれません。
また、何が未学習なのかを知ることにもつながります。
ぜひ、ピンポイントの
「今」
だけを見るのではなく、過去からの歴史を含めて引き継ぎをしてください。
時間が無くて、今すぐできずとも、少しずつでも知る努力を重ねてみてください。
宇佐川研
植竹














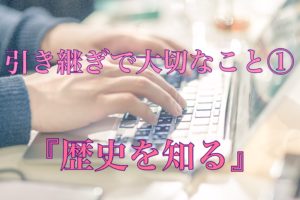
コメント