『心をつなぐ』
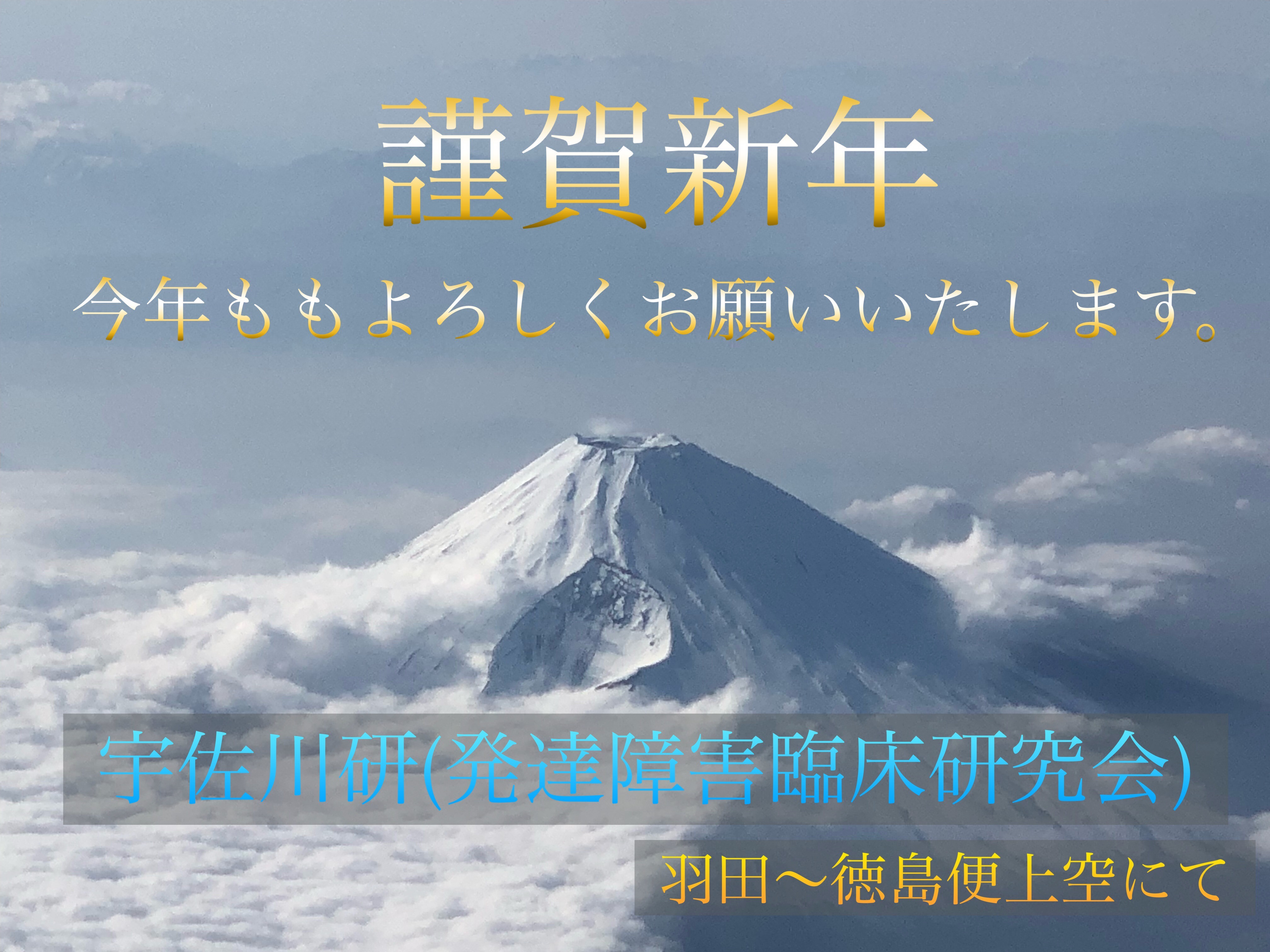
『心をつなぐ一年に』
明けましておめでとうございます。
今年も宇佐川研をよろしくお願いいたします。
夢と目標
初夢はどんな夢でしたか?
私は残念ながら徹夜で作業をしてしまったので、初夢は見れませんでした。
でも、私の中では、夢もありますが今年の目標に進んでいます。
夢に期限を切ると目標に変わります。
2019年 宇佐川研が目指す先
今年の宇佐川研の目標は「つなぐ」です。
ぜひ皆さまも、夢を夢で終わらせずに、叶えていただきたいと思います。
昨年一年間で、宇佐川研(13県)、実践研(東京のみ)と合わせて38回の研究会を開催し、のべ2000名の方にご参加いただきました。
ご参加いただいた方からは、子どもたちのつまずきの「なぜ?」が見えてくるようになりましたとか、
「我が子は、できない子ではなく、誰よりも頑張っていた子」であることが分かったなど、
お子さんの捉え方が変わったという声をたくさんいただております。
しかしながら、全国のお母様からは、様々な悩みのご相談をたくさんいただきました。
いろいろな支援機関に相談しても、「様子を見ましょう」と言われるだけ。
相談に行ったのに、子育てのせいにされ学校へ行けなくなってしまったケース。
自傷行為により、自らの身体を傷つけてしまったケース。
一人で悩み、苦しみ、辛い思いをされている方が、まだまだたくさんいらっしゃることを痛感した一年でした。
発達の知識を少しもってさえいれば、そんなに悩む必要もないことがたくさんあります。
2019年は、宇佐川研を通して、支え合える実践家仲間をつないでいくことをめざします。
そのためにSNSの活用など、情報を本当に必要としている方に届くような仕組みを整えて行く予定です。
今いるメンバーだけではまだまだ成し遂げられない目標です。
そして、お一人お一人が強い意志をもたないと正しい支援をやり通すことも難しい現実です。
例えば、都内のある区は、公立小学校・幼稚園からブランコが撤去されました。
理由はケガをしたら「危ない」からです。
しかしながら、揺れ遊具で遊ぶことをしなかったお子さんの発達こそが危ないことになることを知らないのです。
このような、子どもを育てにくい環境の中で子育てをしなければならない状況において、ますます悩みを抱えるお母さんが増えてしまいます。
研究会に依存しても何も生まれるものはありません。
実践家の心の在り方
宇佐川研は、実践をして良い結果を出して行くことにこだわった研究会です。
支援の輪をつなぐ中で、実践を通して、お子さんが過ごしやすく変化して行くリレーションをつないでいきたいと思っています。
ぜひ、志の高い皆様のお力をお借りし、高めていただくことで、一年後に皆さまの地域のお子さんの笑顔が増えること、お母さんの笑顔を増やしていきたいと決意しています。
実践で結果を出すには、
「実践家としての心の在り方」
が必要になります。
年末に行われた実践研で研究会会長の木村順が締めの言葉として、「実践家の在り方」について話しております。
その動画を新春のメッセージとして送らせていただきます。
人によっては厳しいと受け取られるかもしれません。
しかしながら、子どもたちの将来を創る支援者として必須の内容です。
2分の話の中で、ぜひ皆さまお一人お一人の目標を考えていただきたく思います。
「実践家の在り方↓動画はこちらから↓」
皆さまにとひまして、そして、関わるお子さんにとりしても、幸多き一年になりますことを願っております。
本年もよろしくお願い申し上げます。
宇佐川研(発達障害臨床研究会)
代表 植竹安彦














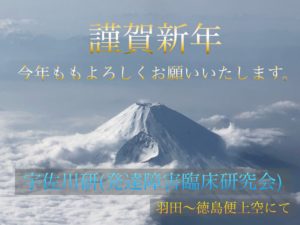
コメント