3歳児のイヤイヤ期はいつまで続く?ひどい場合の対処法ってある?
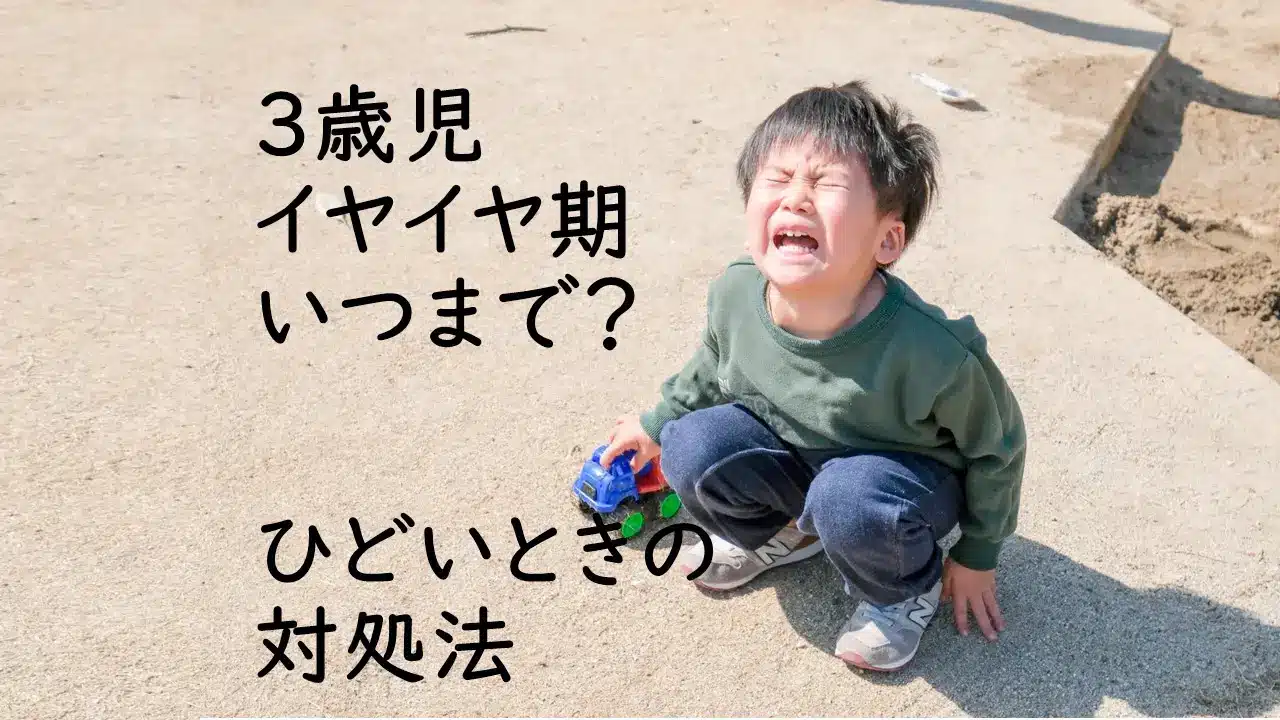
魔の3歳児とも言われることもありますが、子供が3歳くらいになるとイヤイヤ期や反抗期に突入します。
このイヤイヤ期や反抗期は子供が成長している証でもありますよね。
とは言っても、
「うちの子はイヤイヤ期がひどいのかもしれない」
「イヤイヤ期がいつまで続くのか心配…」
このように思ってしまうこともあるかもしれません。しかし、この3歳児のイヤイヤ期は多くの親御さんたちが通る道だと思いますので、ぜひ気落ちしないようにしたいものです。
「そうはいうけど…」
いざイヤイヤ期を体験すると気が滅入ってしまうことも確かにあります。そこでここでは、そんな3歳児のイヤイヤ期の対処法などについて考えてみましたので参考にしていただければと思います。
3歳児のイヤイヤ期はいつまで続く?
イヤイヤ期の期間は個人によって様々ですが、一般的によく言われているのは、早くて1歳半位から長くても3、4歳くらいには終わることが多いです。
また、イヤイヤ期は3歳が多いと思われているのですが、実は2歳児がピークと言われています。
その理由として考えられているのが、2歳頃になると徐々に自我が芽生え始めて自分の想いも主張もできるようになってきますよね。
その自己主張が強くなることで、私たち親の言うこともあまり聞かなくなる事が多いのです。
ただ、中には、
「え?うちの子はイヤイヤ期なんて無かったかも。」
このように感じている人もいるかもしれません。もちろん捉え方次第ではこの様に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
とは言っても多くの親が体験する我が子のイヤイヤ期。このイヤイヤ期がひどいと感じる場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
イヤイヤ期がひどいと感じる…。そんな時の対処法は?
イヤイヤ期真っ只中の場合、子供には何を言っても聞いてくれない…そんな時があります。
そんな時はとにかく一息ついて、子供のボルテージが下がった時にもう一度伝えたい事を言ってあげることが大切だと思います。
また、子供の言い分に共感してあげることで子供も”自分の意見が通った”と感じて落ち着いてくれるかもしれません。
先輩パパやママの中では、
・とにかく落ち着くまで見守る
・一呼吸置いてから声かけするようにした
・子供の言うことに共感してあげた
など色々な対処法を考えていらっしゃいます。
対処法というよりもどうすれば自分にもストレスが少なく、子供も伝えたい事を受け入れてもらえるか?に注力しているようにも感じました。
そして共通していたのが、”怒鳴りつける様な言い方だけはしないように気をつけた”と言う事です。
ただでさえイヤイヤ期突入で感情が高まっているのに、怒鳴りつける様な言い方をすると子供もさらにヒートアップしてしまいますよね。
そうならない様にするためにも子供のペースに合わせるのは大切な事だと思います。また、イヤイヤ期と同時期によく言われるのが、「赤ちゃん返り」。
これについても少し触れてみたいと思います。
赤ちゃん返りとは?
赤ちゃん返りという言葉、誰もが一度は聞いたことがありますよね。
主に下の子が生まれた時に上の子が今までなら難なくできていたことも赤ちゃんのようにできないふりをしたりしてママに甘えたりすることがあります。
このような言動を一般的に赤ちゃん返りと言っています。
要はかまって欲しい、ママの愛情を確かめたい…そんな想いもあって赤ちゃん返りを起こしてしまう事があるのです。
下の子が生まれた時の他にも、外で遊んでいて「赤ちゃんって良いな」と子供自身が感じた時も赤ちゃん返りをすることがあります。
なので子供が急に赤ちゃん返りのような言動を取ってきたら、甘えたいんだな。と思っておくと私たち親自身も気が楽になるかもしれませんね。
赤ちゃん返りの特徴
赤ちゃん返りの特徴としては、
・急に赤ちゃん言葉を使い始める
・甘えてわがままを言い出す
・いつもは普通に歩いているのに急にハイハイで移動
などが一般的に言われている言動です。
その他にも普段しない赤ちゃんっぽい事を始めたら赤ちゃん返りの可能性を考えてみると良いかもしれませんね。
まとめ
3歳児はいろいろな成長を私たちに見せてくれるので、楽しくもあり、そしてとても大変な時期かもしれません。
しかし、誰もが通る道だと思ってしまえば割と辛抱できるものです。
ぜひ、イヤイヤ期に突入したからといって悲観的になるのではなく、あくまでも子育てを楽しむスタンスで身構えておくと、割とすんなりこの時期を乗り越えることができるかもしれません。














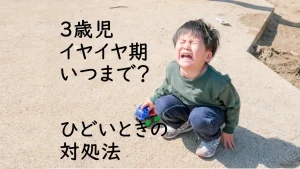
コメント