中心軸を育てる意味

宇佐川研のオンラインサロン「発達支援ドットコム」のメンバーの子どもを捉える目が急速に高まっています。
サロンでは月に2回、公開カンファレンス(ミニケーススタディ)があります。
ケースのお子さんの育てるべき視点として、保護者の参加者からも「中心軸」という言葉がさらっと飛び出てきました。
感覚統合を学んできている方であっても、なかなか育てるべきポイントの一番目に「中心軸」と言ってのける方は少ないのではないでしょうか?
「中心軸」ってなに?
中心軸とは、言葉の通り人の身体の中心を指します。身体の中心と言っても、鼻が通っているあたりをただ単に中心と言っているわけではなく、右脳と左脳の真ん中、中心を脳機能として育てていく視点となります。
脳の中で中心が育つ前は、右は右、左は左と別々にしか使えないような身体の使い方となります。イメージしやすい状態像としては、ご飯を食べるときにお茶碗を持たずに、片手だけで食べているような姿です。
ハサミを使っている様子では、反利き手側が上手に使えず、ハサミだけを動かすような危ない切り方をしているようなお子さんの姿です。
脳の中の中心が育つことで、右脳と左脳が連動し、脳機能としても脳の各部位で役割分担されている機能が連動して使えるようになります。パソコンでいうと、大幅なアップデートがされたような状態に変化します。
中心軸が育ってくると、お茶碗を自然と持って食べるようになったり、歩行も回旋動作が加わりスムーズな歩行へと変化します。
中心軸のイメージとしては、でんでん太鼓の中心の棒が身体に備わる感じです。もしでんでん太鼓の棒がグニャグニャしていたら、でんでん太鼓は回転することができず、太鼓を鳴らすことができません。軸ができるからこそ、身体の回旋を伴う、歩行、投球などパフォーマンスの高い動きを生み出せるのです。
発達の意味性をつなぐ
感覚と運動の高次化理論には、「発達の意味性」ということばが出てきます。何かが発達するということは、派生的につながっていく発達がまた現れます。逆に、何かの力を育てたいと思ったときは、その力のベース(土台)となる力が何であるのか見極められる必要があります。
もし、文字を書くという力を育てたいとなると、文字が書けるようになるまでの土台となる力としてどのような力がどのような順番で積み上げる必要があるのか知らないといけません。
例えば、滑らかに鉛筆を操作するためには、三指握りが必要です。三指握りができるようになるためには、手の中の安定を生み出すために、小指と薬指(尺側)の安定が必要です。手の中の土台ができることで、ようやく人差し指、親指、中指の3本が自由に動かせるようになり、三指握りによる滑らかな鉛筆の動きが作り出せます。
この手の中の土台を作るためには、肘、肩、肩甲骨の安定が必要であり、さらには、体幹の安定が育っていてこそ生み出せる、上肢の安定となります。
また、書字には運動面だけでなく、空間を把握する力であったり、頭の中に思い浮かべる力などの認知能力も必要です。頭に思い浮かべる力の土台をさかのぼっていくと、触覚が適切に機能し、目と手が協応した動きが必要となります。
このように、多岐に渡る力が積み重なり合い、絡み合っているのが人の発達です。
中心軸が育つためには?
中心軸が育つと、脳機能が高まったり、身体の左右が連動した複雑な動きができるようになったりします。
では、中心軸を育てるためにはどのようなことをしていく必要があるのか?
それは、回る、跳ぶ、揺れるなどの平衡感覚をふんだんに使った運動や遊びの経験が必要となります。
だからバルンポリンをおススメしているわけです。
そのほかにも、回転するような運動遊び、ブランコのような水平の加速度が入る遊びなども有効です。
子どもの一瞬の姿から
今回はサロンのミニケーススタディの一場面で、片足立ちが苦手という場面がありました。片足立ちというのは、重心を左右の一方にずらして姿勢を保持する動きです。そもそも、身体の中心が育っていなければ、左右は育ちません。だから、この一場面を見ただけでも、まだ身体の中心が育っていないのだなと読み取れるのです。
このようなお子さんの一瞬のしぐさに、発達の様々な意味が読み取れます。サロンのメンバーは半数近くが保護者です。わが子のためだからこそ、一生懸命学んでくださっています。そして、他のお子さんの成長の様子から、わが子に生かせる視点をたくさん持ち帰っていただけるのが、宇佐川研のケーススタディや、サロンの公開カンファレンスです。
どんなに知識が豊富でも、目の前のお子さんのどの動きにその様子が表れているのか読み解けなければ、机上の空論で終わってしまいます。
せっかく学ばれた知識を、目の前のお子さんの姿と結びつける練習を一緒にしていただけたらと思います。
子どもたちは、いつもそのメッセージを発信してくれているのですから。




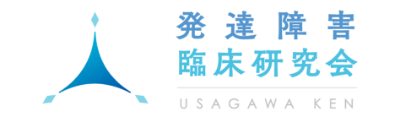






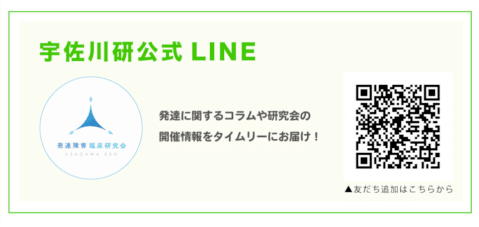
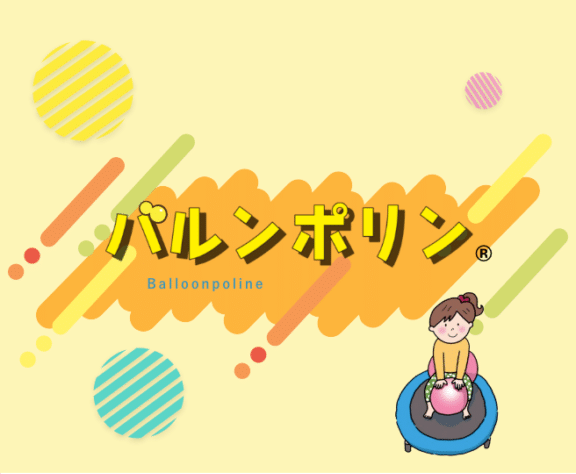


コメント