「昼寝なんて嫌いだ!」

「昼寝なんて嫌いだ!」
宇佐川研に出合う前、行動の理由を何も知らなった私は、お昼寝前に騒いだり、すぐにむくっと起き上がったりするお子さんに、とてもイライラしていました。「何で寝てくれないの?」「眠いなら寝ればいいでしょ!」と思っていました。当時の自分には彼らの行動は理解ができず、「寝るよ(怒)!」と半ば押さえつけて寝かせていました。マルトリートメント(不適切な養育)です、ほんとに。いま振り返ると、反省と後悔とお詫びしかないです。
保育士として、側に保護者が見ていたとしても、保護者が安心していられる、自然体の保育をする自分でありたいと思いながら、「何なんだ!こんな自分は!」と自己嫌悪を抱えつつ、それでも毎日「寝るよ!」と押さえつけてしまう…。自分で自分を処理しきれずに、担任をおりることにしました。
担任をおりてフリーになって、多く関わるようになったのが、クラスの一斉活動になじめないお子さん達。その中の一人の加配となり、私の加配人生?スタート。悩んで、色々しでかすお子さん達の後を追ってばかりの日々でしたが、ある日(笑)、宇佐川研に出会いました。学んで、今まで理解できなかった行動が理解できるようになって、本当に毎日仕事が楽しくて、本当に子ども達が可愛くて仕方ない。
だから。
今、イライラしたり、悩んでいる保育士の皆さん、そして夜寝ないお子さんに悩んでいる保護者の方々に読んでいただきたいなぁ、と思っての、保育士にゃーのつぶやきです。

お昼寝の時間がトラウマ?
保育園に通った経験のある人で「お昼寝の時間が大嫌いだった」という方はいらっしゃいませんか?
私の職場、保育園でも何人かそういう人がいます。
なぜって?
みんなと同じようにスムーズに眠れないからです。
眠れないのに、「寝なさい!」と怒られる…。そんな経験を持つ方も少なくないのではないでしょうか?私の友人に、保育園のお昼寝の時間が「トラウマになっている」という人もいたくらいです。
理解できない行動
保育園では、お昼寝の時間になると、ハイテンションになって騒いでしまうお子さん、お布団の上で体操のように足をバタバタさせてしまうお子さん、静かにして欲しいのにしゃべり続けてしまう、歌を歌ってしまうお子さん…スムーズに入眠できないお子さんがたくさんいます。
本当は遊んで疲れて、ご飯を食べて、眠たいはずなのに…なんで?眠いなら寝ればいいのに!大人側からしたら、理解できない行動ですよね。

行動には、必ず理由があります。
みなさんは、すごく疲れて「寝よう」と思ったときに、逆に神経が立ってしまって、扇風機の音や、エアコンの音、少しの光、少しの布団の違和感などで、寝づらくなった経験はありませんか?
自分は寝たいのに、眠れない!寝たいのに「眠れない」と思うと余計に「寝なくちゃ」と思って、寝ることができなくなってしまいませんか?
身体や脳が疲労すると、覚醒レベル(脳の活動レベル)が低下して、感覚が過敏になることがあります。そして、情緒をコントロールする力も落ちてきます。「少しのことが気になって仕方がない」「ちょっとのことでハイテンションになって情緒のコントロールがきかなくなる」ということが起こります。
徹夜をした時に、酔っているわけではないのに、友達の些細なことで笑いが止まらなくなる逆ハイテンションもその一例です。これは、私たちの話をしているのですが…実はこの状態が、お昼寝の前に子どもたちが落ち着かなくなる姿、そのものなのです。
すっと寝ればいいのに、少しの音や光で起き上がる。一人がざわざわしだすと、みんなではしゃぎだす、これは覚醒レベル(脳の活動レベル)の低下がもたらす状態です。
心と身体の疲労の回復や健やかな成長のために、お昼寝は大切です。ではスムーズに眠れないお子さん達に、私たちはどう対応したらよいのでしょうか?

行動の理由にアプローチ! ~子どもに寄り添う~
①刺激を減らす。
覚醒レベルの低下で感覚が過敏になっているので、刺激を減らします。
生活をしていれば、刺激があるのは仕方のないことですが、出来る範囲で音や光などの刺激を減らしてあげましょう。
特に過敏になってしまうお子さんは、大人の身体と壁で視界を遮る、頭をなでながら耳を軽く覆ってあげる(触覚過敏のお子さんには触り方に注意が必要です)のも有効です。(しっかり圧をかけて覆った方が、半端な触り方より好きなお子さんもいます)
私は現場で、大人女子用のヘアバンド(無地、黒、100均)を使うこともあります。本人が眼や耳を覆って寝た方が寝やすいことを自覚している場合、自分でアイマスクのようにつけてもらって寝ています。
また、園庭遊びから戻って、入室前後からすでに大泣きしたり、ぐずったり、逆に変にはしゃいでしまうような、コントロールがきかなくなった場合。大人はなんとか気分や行動を変えてもらおうと、あやしたり、叱ってみたり、なだめてみたり一生懸命になってしまいますね。けれども、その一生懸命な雰囲気や、次々に発せられる言葉が刺激になって、余計に泣いたり、興奮してしまうことが多いです。
まずは静かなところに移動して、黙って側に寄り添ってあげてください。背中やお腹に手を当てて、少し圧をかけてあげると落ち着くことが多いです。お話は落ち着いてから、静かな声でゆっくりしたほうが、本人が耳を傾け、自分の頭で考えて行動を切り替えることができます。
大人の表情、声の大きさ、言葉の数も大切な環境の一つ。刺激にもなり、安心材料にもなるのです。
②感覚を整える
どうしても動いてしまうお子さんは、感覚が鈍麻なお子さんで、感覚欲求でじっとしていられない、いわゆる多動の状態です。
生理的に身体が動いてしまう状態なので注意はしません。何回も注意すると「叱られた」感ばかりが残り、逆にその声かけで興奮してしまいます。そういう時は動いてしまう所を積極的に動かし刺激を入れてあげると落ち着きます。足裏を軽く叩いたり、揉んだり、ふくらはぎをさすると、途端に無口になり動きが止まります。
落ち着けるようにウェイトブランケット(重さのあるブランケット)を使うのも有効です。ウェイトブランケット、重くて「小さい子にこんなの使っていいの?」と心配になりますよね。もしもウェイトブランケットを使う事に抵抗があるようでしたら、ぜひご自身で試してみてください。「落ち着く」という感じが実感できると思います。ただ、感触や好み、その日のコンディションなどもあるので、
本人が嫌がる時は絶対に使わないでくださいね。ウェイトブランケットは、発達障がいグッズではなく、もともとは北欧で開発された不眠対策グッズです。
③識別系にスイッチを入れる
「コントロールが効かなくなる」状態は、脳の原始系(脳幹や大脳辺縁系…進化する前の動物的な機能)が優位に働いている状態なので、識別系(大脳新皮質…人として進化した部分=行動や情緒をコントロールする脳)が優位になるようにスイッチチェンジすることが有効です。
幼児だったらお布団にうつ伏せに寝てもらって、背中に文字を書いてあてさせる、乳児だったら簡単な昔話などのお話をするなど、頭を使う活動をして、脳のスイッチチェンジをはかります。そうすると、大人の話を聞き分け、自分の頭で考えることができる状態になります。
泣き叫ぶ乳児さんは、抱っこして大きめにスイングして前庭覚に刺激を入れながら、歌詞のある歌をゆっくり歌うと、歌詞を聞こうとするので、落ち着くことが多いです。
④気持ちに寄り添う
自分が眠れない時に「寝なさい」と言われると、辛いですよね。発達支援でも保育全般でも生活全般でも、自分がやられて嫌なことはしないことが大切です。相手の立場に立って「相手の脳になって考えてみる、感じてみる」ことが大切です。「眠れない時もあるよね」と気持ちに寄り添い、側にいるだけで安心して眠れることも多いです。
お昼寝バトルがなくなりますように…
保育園によって、日課も違うので、必ずそうだとは言えませんが、多くの保育園では「寝かせたい大人」と「寝れない子ども」のお昼寝バトルが繰り広げられているのではないでしょうか?
お昼寝の時間は、忙しい保育士に与えられた唯一の会議や事務仕事の時間です。保護者に連絡帳で丁寧に説明したい、こんな記録も残しておきたい、小学校に提出する書類を書かなくちゃ!行事の準備が間に合わない!眠れなくても静かに出来ればいいのですが、そうもできない子ども達(笑)。周囲にいるお友達を起こして欲しくないので、静かにしていられないお子さんほど、「寝なさい」ターゲットにされ、そこでバトルが始まってしまうのだと思います。
今、自分はクラスで眠れない子は「無理に寝なくていいよ」というスタンスをとっていますが、やはり体は寝たがっているお子さんは、環境や感覚のアプローチをして眠れるように支援しています。それが、すべて子どものためかというと、やっぱり自分が事務仕事したい気持ちもあるかも…。複雑です。
それでも、「お昼寝がトラウマ」なんて将来言わせたくない。子どもとバトルはしたくないな、と思います。寝たくない気持ち、眠れない気持ちに寄り添いたいと思います。それでも、時々「寝るよ!」と言ってしまう自分、とほほ…。
年齢は重ねておりますが、中身が未熟な保育士にゃーの格闘は続きます…。










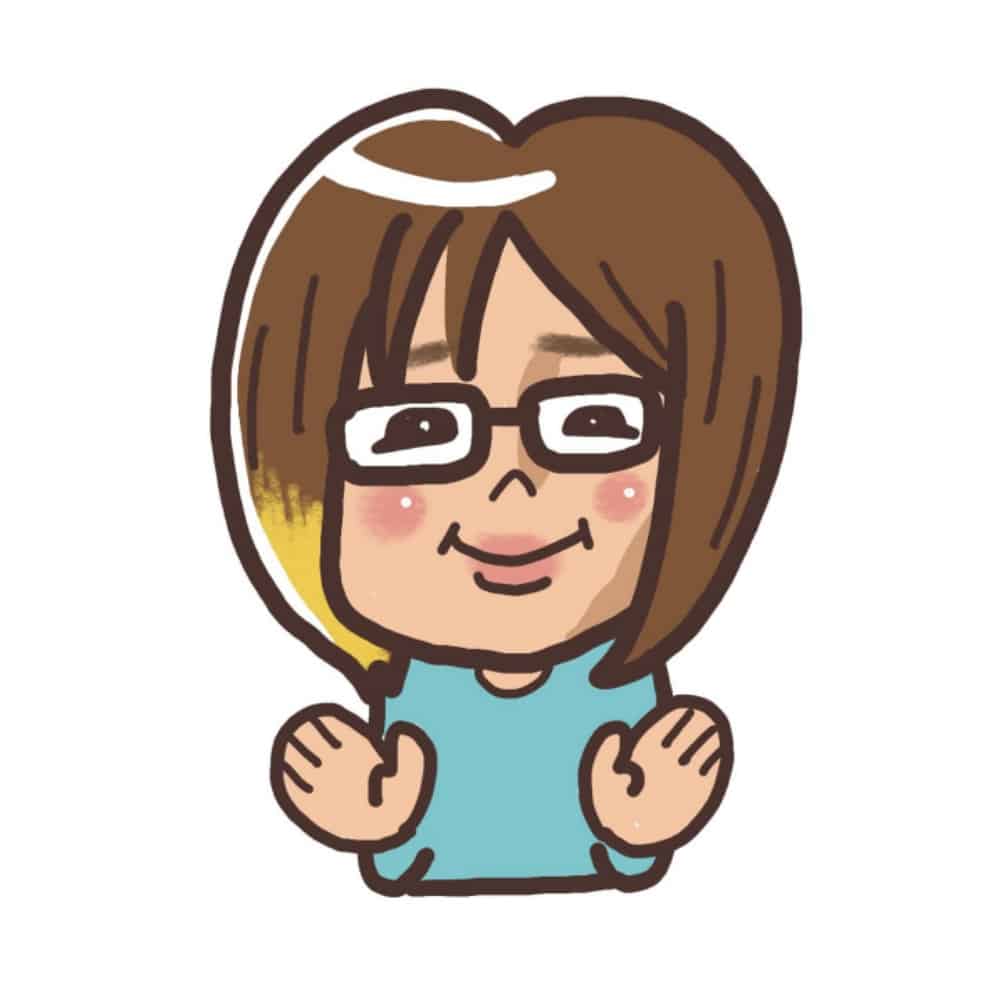





コメント
コメント一覧 (8件)
初めまして、加配保育士をしています。
まさに、今日のお昼寝バトルに疲れてこのサイトに辿り着きました。
寝るのに時間がかかる子で本人が寝ようと思っているのはわかるけど、ふざけているように見えてしまう。いろんな先生に怒られて泣き出して、どうしたらいいものかとモヤモヤしながら帰ってきました。
私は担任ではないので思い通りにはいかないかもしれませんが、担任の先生も悩んでいるので、相談しながら紹介されている方法を試してみたいと思います。
コメントありがとうございました。嬉しいです。
お昼寝バトル…大変ですよね。
自分の経験上、発達に特性のあるお子さんで覚醒レベルを落としにくく、一回落ちると上げにくいお子さん(→寝付くまですごく時間がかかり、寝てしまうと今度は起きるまでに時間がかかる)は、多いです。
ただ、大人が「寝なさい」とムキになればなるほど、その雰囲気や言葉の強さが刺激となり、余計にお子さんの情緒が乱れて眠れなくなることが多いようです。
寝なくてもいっか、ちょっとふざけてもいっか。でも、寝ているお友だちは大切にしようね、静かにしようね、くらいに、大人がゆる~く構えた方が、お子さんの情緒も落ち着くようです。
自分が所属する園の異年齢クラスでは、ウェイトブランケットと、ダンボールを使った壁を多用しています。壁は視界をさえぎり刺激を減らすとともに、プライベートスペース…個のスペースを確保するイメージです。ただ、大人からも見えづらくなるので、寝たら壁は取り除き、様子を目視できるようにします。
感覚鈍麻なお子さんは、足をマッサージするとすっと落ち着き寝入ることが多いです。背中をトントンと叩くことで寝入るお子さんもいます。手をぎゅっぎゅっと握ってあげると寝るお子さんもいます。それぞれの「つぼ」?は試行錯誤がいると思います。
幼児の場合、ですが、騒いでしまうタイプのお子さんに対してよくやるのは
「寝よう」と言わないで「足が速くなるようにマッサージしてあげるよ」と言って
うつ伏せになってもらって、足裏や脚全体をマッサージすることです。
ぴたっとしゃべらなくなり、リラックスしてくれることが多いです。
ついでに、足裏、足指にアプローチ(植竹先生のイロイロ動画を参照してください)も
できるので、一石二鳥です。
寝ないことは怒られることじゃない(騒ぐのはNGですが)…自分も寝たくて寝れない時に怒られたら
踏んだり蹴ったりな気持ちで悲しくなりますよね?
寝たくない、という気持ちも尊重する…自分も寝たくない時に寝なさいと言われたら嫌ですよね
そんなことを頭の中に置きながら…試行錯誤してみてください!
コメントありがとうございました。
お昼寝のとき、とにかく身体がとまらない年少さん。お布団に横に成ることも駄目、座るのも駄目、歩き回り、歌い出す、話し出す、トイレトイレが始まり挙句の果てにお布団の上でお漏らし。耳を塞ぐ事も駄目。寝ている子供を起こしてしまうこともあり。保護者さんはお昼寝をしなかったら夜が寝れるから、お昼寝しないと嬉しいと言っています。
コメントありがとうございます。毎日のことなので、しんどいですね。
もし大人の配置ができるのであれば、お昼寝無し、と決めてしまうとお互いが楽になるかもしれません。
そうでなければ、午睡前に落ち着きが無くなる行動の理由を考えて(覚醒レベルなのか、感覚なのか、精神面なのか)そちらにアプローチしてはいかがでしょうか?ヒントはこのサイト内にも!
ファーストステップとして、「寝ないでいいから布団の上で静かに遊ぼう」からスタートしてもいいかもしれません。
お子さんも、先生も、少し気持ちが楽になりますように…。
コメントありがとうございました。
こんにちは。4歳児女の子。全てにおいて、素直に動けず笑。手を繋いでうまく話しながら連れていっても、キャーと大きな声で大騒ぎ。
お昼寝も布団には、数分しか入れず、マッサージしても拒否。大きな声できゃーー!と大騒ぎ。抱き抱えてないとおもちゃを出したり。
先生達も色々と試行錯誤しています。
なんなら、起こしておけば良いのでは?と思う私ですが、担任ではないので…
どうしたものか…
一部屋、ねないこのお部屋を作ってみたら、良いのにと思ったりしてしまぃます。
覚醒が高すぎるように一見感じられますが、実はちょうどよいところまで高まり切らないで日中過ごしている子のように思います。
ブランコやトランポリンなどが特に好むようなところがあれば、平衡感覚の低反応が根っこにあるように思われます。
感覚面の取り組みが必要そうではありますが、情報が足りないので何とも言いきれません。跳ぶ、揺れる、回る運動遊びを午前中にふんだんに取り組んでみて(酔うなどの症状が無ければ)ください。
同じくフリーとして加配保育士をしています。
三歳児クラスでおしゃべりと歌が止まらず、布団でじっと出来ずに周りの子にちょっかいを出してしまうので普段は抱っこで寝せていますが、それでも寝るまでは歌が止まりません。言葉はおうむ返しのような感じでこちらの言葉の理解ができていないのかお昼寝の時間は静かにしようねと伝えても伝わっていなそうです。
寝てもアトピーもあるからか扇風機の風のような少しの刺激で目を覚ましてしまいます。
突発的にクラスから飛び出してお遊戯室まで走っていってしまうこともあるのでどのように対応するのか担任の先生と頭を悩ませています。
おしゃべりが止まらずというのが、そのお子さんを特徴づけている部分があります。
たぶん、おしゃべりをすごくされている割には、その内容の理解度はあまり高くないのではないかと思います。聴覚ー言語系の空回り状態となっていて、視覚からの情報がちゃんと処理でき辛い状態のお子さんかと思います。
跳ぶ、揺れる、回るが、異様に好きか、真逆の超嫌いかのどちらかの場合、目の使い方に非常に苦手さがあります。そうすると、視覚からの情報を処理できておらず、耳からの情報で生活しやすくなります。同時に、平衡感覚の反応性が良くないことも多く、覚醒のコントロールも良くなく、お昼寝の少し暗くなった状態が一番激しく動き回りやすくなるなど起こりやすいです。
感覚面の読み取りが必要なお子さんです。このままいくと、学齢期で読み書きにも支障が出やすいので、早期に支援を入れて頂きたいなと思います。