「1枚の写真からの支援と合理的配慮②」東京宇佐川研1月度より
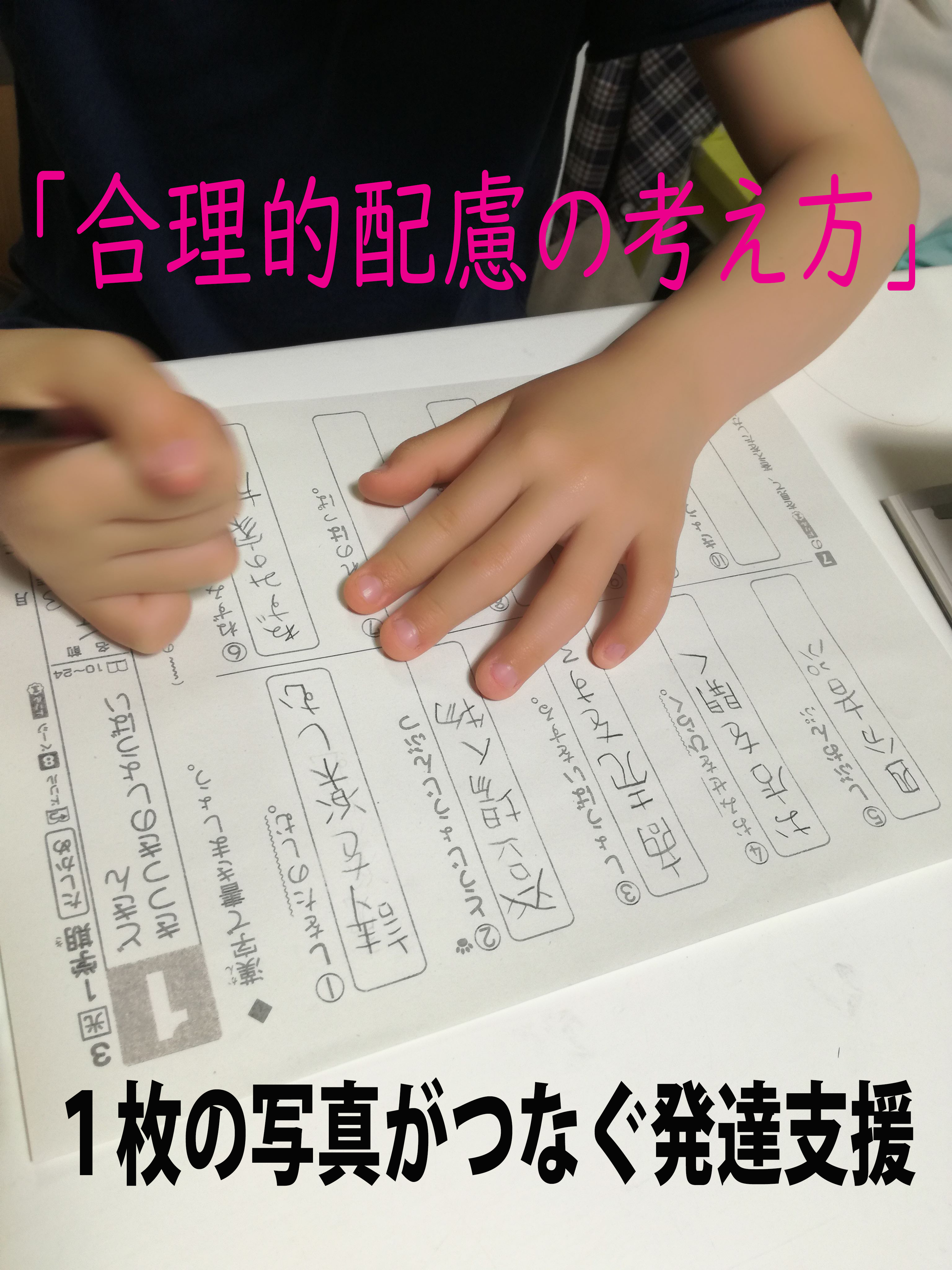
読み書き支援と合理的配慮
東京宇佐川研の報告の続きとなります。
前回の投稿はこちらから↓
https://goo.gl/93CeB6
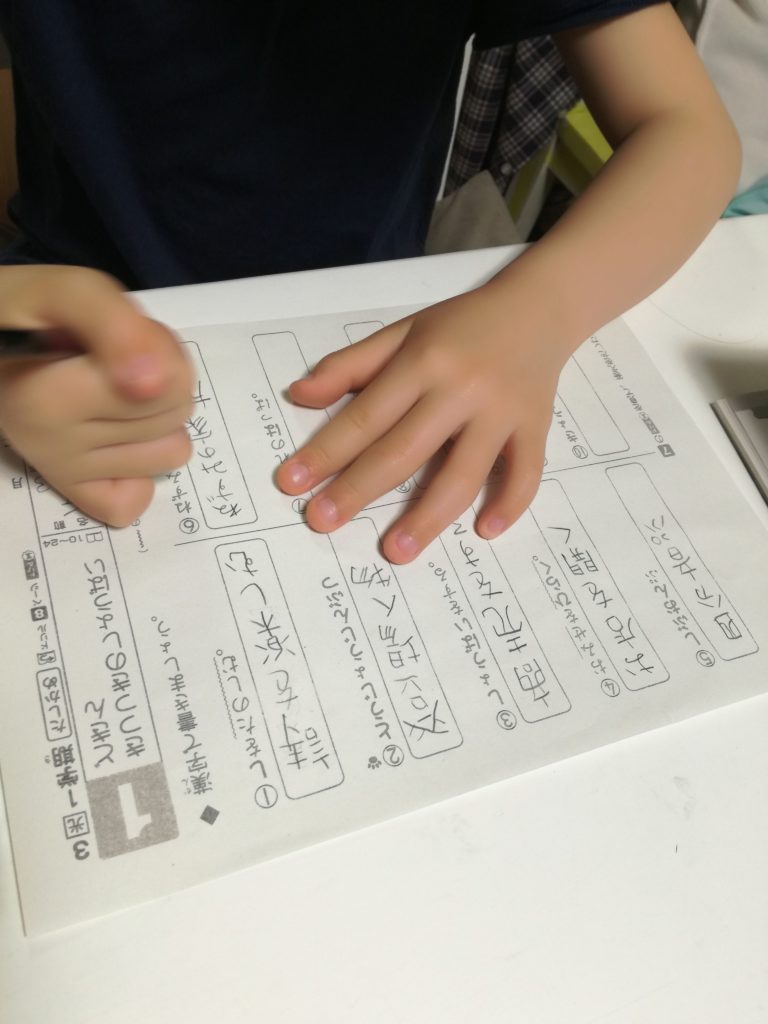
身体の育ちと心の関係
ご家庭での支援の中で、お子さんの姿勢や書字の速度なども高まってきました。
しかしながら、お子さんとしては毎日全力で回りの友達についていこうと必死な状態です。
大好きなお母さんを心配させまいと、お母さんからのアドバイスにも全力で耳を傾けそして運動療法にも取り組んできました。
しかしながら、ご自身のつまずきの改善と共に、心も育ちつつ少しずつお母さんとの距離感も変化を示していきます。
少しずつ母から離れて自立していく姿です。
学校で弱い姿を見せないように、お子さんは全力疾走の生活。
家に帰ると疲れ切ってしまう様子からお母さんの心配はやみません。
それでいて、お子さんは母のアドバイスから距離を置こうとします。
いろいろな支援機関のアドバイスもあり、適切な支援を提供してくださる眼科との出会いもありました。
書字なども良くなりつつも、依然として苦手さは強くあります。
そこで学校へ相談をしてみるものの、本来の合理的配慮とは違った見解がでてきてしまいます。
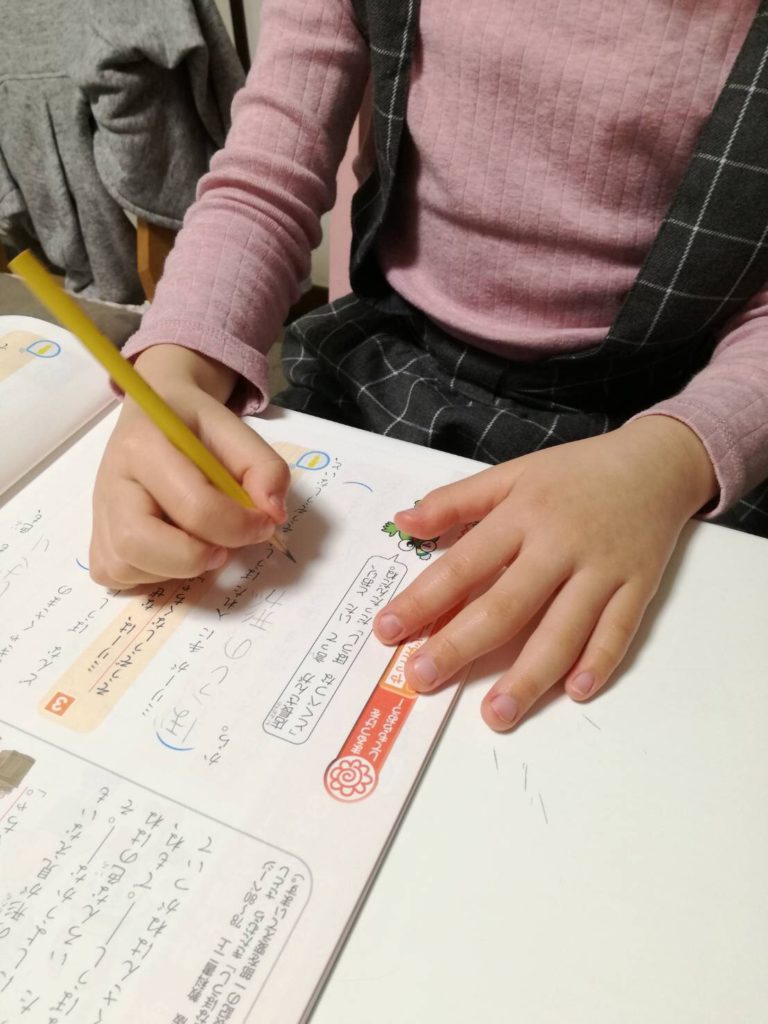
一人一人の合理的配慮
学校の対応は「平等」という 考え方の捉え違いです。
書字が苦手であるということを相談してみると、理解を示してくれつつも最終的には
「努力すればできる」
「一人だけ認めるわけにはいかない」
「全員一緒」
という発想が根強く、お子さんは努力の限界が来てしまいました。
例えるなら、軽自動車で坂道をアクセル全開で走る続ける毎日。
少しでもアクセルを緩ませようとするなら、あっという間に坂から転げ落ち、そこで言われるのが「努力が足りないから」「やってできないはずはないだろう」というニュアンスの言葉でした。
本来の合理的配慮の発想からすると、みんな同じではなく、
「一人一人の実態に応じた配慮」のはずです。
「平等」よりも「公平」を目指すべき配慮です。
一人一人、事情や配慮のポイントは違います。だからこそ支援すべき内容は個別に違って当然です。
視力が悪いからといって、視力の悪いお子さん全員に同じ度数のメガネを渡すことはしないはずです。
読み書きなど、うまくいかない理由がまだはっきりと認知されていないために、分からないから一律の配慮というのはおかしいのです。

もう一度理解を(合理的配慮とは)
合理的配慮についてもう少し理解を深めていってみませんか?
民間企業などはまだ努力義務ですが公的機関は法的義務となります。まず、この違いは大きな違いです。

合理的配慮を分かりやすく示してくださっている自治体がありますので、資料をこちらに添付いたします。
目黒区教育委員会より
『合理的配慮の提供事例集』
バリアフリーからユニバーサルデザインへ
バリアフリーはそもそも健常者側の立ち位置からの発想です。車いすの人が使うには段差があっては使い辛いので、一度階段を壊してスロープを作りましょうというような考えです。
でも、ユニバーサルデザインの発想でいくと、最初からすべての人が使いやすいように作っておきましょうとなります。
合理的配慮についても、様々なお子さんの困難さを受け止めたうえで進めていけば、もっと柔軟に進めていけるのではないでしょうか?
子どもたち一人一人に家庭で、学校で、社会でそれぞれの場所で輝けるような「居場所」をもって欲しいと思います。
そのためには、一人一人の能力を引き出すための、一人一人に応じた支援が当たり前に受け止められる心の柔軟さが必要なのかもしれません。
何もお金をかけるだけが支援ではないと思います。
アイディアとその場におけるほんの少しの協力がありば叶うものばかりだと思います。
宇佐川研の役割
私たち宇佐川研は実践家仲間です。
人への責任転嫁や批判批評は実践家のやることではありません。
私たちにできることは、発達の仕組みやメカニズムをお伝えしていくことです。
理解が得られれば、具体的な支援が見えてきます。
そして、理解に基づく支援を実践できる仲間を増やしていきたいと思います。
これからも、全国で困っている子どもたちや、子育てで苦しんでいる保護者の味方となり、そして頑張る支援者を応援していけるように歩んでいきたいと思います。
一緒に歩んでくださる仲間と手をつないでいきたいと思います。
宇佐川研 代表
植竹















コメント