触覚を使って遊ぼう

過敏と鈍麻
娘は現在、4歳7か月。我が子の場合、触覚に対しては、過敏さと鈍麻さがありました。例えば、耳かきや歯磨きを嫌い、大人が抱きしめると自分から離れる子でしたが、その反面、服が濡れてもへっちゃら。泥遊び、スライム・粘土、いわゆる感触遊びは大好きで、年中、公園では裸足で遊ぶ子でした。
耳かきなど、家庭では到底難しく、耳鼻科で大人5人がかりで押さえつけないとできないくらい、触覚過敏があって大変でした。そんな状態を打破できたのは、4歳0ヶ月。初めて家庭で押さえつける必要なく、耳かきができるようになったのです。
触覚の例
そもそも、触覚のお話は、初めて宇佐川研に参加した際、植竹先生から「ポケットに手を入れた時、いろんな物の中から必要な物を取り出せますよね?」という例を紹介してもらいました。大人は容易にできるのですが、果たして娘はできるのか?!そんな想いに駆られ、今回やってみました。
モンテッソーリ教育では
娘の通っている幼稚園は、モンテッソーリ教育を取り入れている園なのですが、そこでは「ひみつ袋」というお仕事があり、まさにこの「触覚」を使ったお仕事なのです。2人でやることもできるようで、小さな袋に小物を入れ、相手と同じ物を袋から取り出すのです。
触覚を使った遊び1
今回は、モンテッソーリ教育のやり方を真似て、やってみました。袋の中に家にあった指輪、スーパーボール、50円玉、1円玉、消しゴムを入れました。 まずは、名称がわからなくては意味がないので、何が入っているか見せて名前を伝え、私の持っている袋の中から、私が1つ出して見せたのです。
すると、娘はとても興奮した様子で、自分の持っている袋に手を入れました。やってみると、袋の中を見ながらやりたくて仕方がない様子。結局、今回は、素材や形も違うのでしたし、容易に正解できました。
触覚を使った遊び2
先ほどの取り組みで、指先に意識を向けることができているようだったので、他のやり方でも挑戦してみることにしました。バラエティー番組でよく見かける、箱に手を入れて何が入っているか当てるゲームです。
さすがに虫や動物は、入れませんが、中に入れるものは、娘が名称を知っているもの、よく使っているものにしました。
箱がなかったので紙袋で代用し、紙袋の中身が見えないように紙袋の口を塞ぎました。私がまず最初に袋の中に入れたのは、「タオル」でした。
そもそも見えない物の中に手を入れて触るなど、触覚防衛があれば、難しい遊びですが、娘は好奇心が勝り、のってきました。
こちらのゲームは、意外と中身を見たがらず、目を瞑って触る姿も見受けられました。この視覚的な情報をできるだけ遮断して、触覚に注意を向けている姿を見ていると、たまらないです。
触る→答える→正解を見るという流れで、次の物を入れようとしたところ、娘に「次はママね」と順番がまわってきたではないですか。
あなたの番です
ぶっちゃけ私はやる予定ではなかったのに…と心の中で思う反面、娘が選ぶ物も楽しみでした。いざ、自分の番になった時、袋の中に手を入れるのに躊躇するかな?と予想していたにもかかわらず、意外と手を入れるのは平気でした。
手を入れてみると、感触が冷たく、固い。大きさは意外と大きい…。
「もしかしてキャベツ?!」
大正解でした!
楽しむコツ
実は、私、子どもと遊ぶのがとても苦手なのです。ですが、子どもと遊ぶのが苦手な私が、どうやってひとりっ子の我が子と楽しめるかというコツをお伝えしたいと思います。
それは、「実験」です。実験にしてしまえば、大人の私も楽しめるのです。これをしたらその物は、どうなるかな?娘は、どんな反応をするかな?そんな思いで関わると、楽しくなってくるのです。
やってみると、キャベツがこんなに冷たいんだ、なぜレタスとキャベツが見分けられたのだろう?葉の固さかな?など、やってみてわかることがあるのです。
今回も自分の番がなければ、一方的にやらせて終わりでした。でも子どもと一緒にやることで、遊びになるような気がします。
まずはやって見せる
そもそも触覚防衛があった娘が、やってくれないと意味がないので(見てくれるだけでも大きな大きな一歩なのですが)、初めてのことに挑戦する際は、いつも私が楽しそうにやって見せるようにしています。スライム遊びやハンモックなども、まずは私が楽しそうに遊んで見せることから始めました。それでもだめなら、今じゃなかったと潔く諦めます。
我が子の場合、「怖い」という体験をしてしまうと、半年以上やりたがらなくなったり、苦手意識に繋がるので無理はしないと決めています。
触覚防衛が改善すると
結論、この遊びを通してでは、娘がどこまで触覚防衛が落ちているのかわかりませんでした。そもそも我が子は、特に触覚防衛を落とすための取り組みはしていません。なぜ改善したのか素人なりに振り返ると、娘は触覚の過敏さと鈍麻さがあったので、「公園で裸足で遊ぶ」「お家で感触遊びをやる」をひたすらやったことで、過敏だった部分が改善されたのではないかと推測されます。
実は、最近、少し触覚過敏が落ちてきたおかげで、子どもの方からスキンシップをとるようになってきたんです。触覚防衛が落ちてくると、よくあることなのですが、その姿は、とても愛おしく、可愛いのです。赤ちゃん期、あんなに抱きしめると逃げていくことを思い返すと、今の幸福感を当時の私に教えてあげたくなるのです。
次回は、娘が一番つまずいていた「前庭覚」についても実験という名の遊びで、いろんな取り組みを紹介できたらと思います。最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
まみむめママ









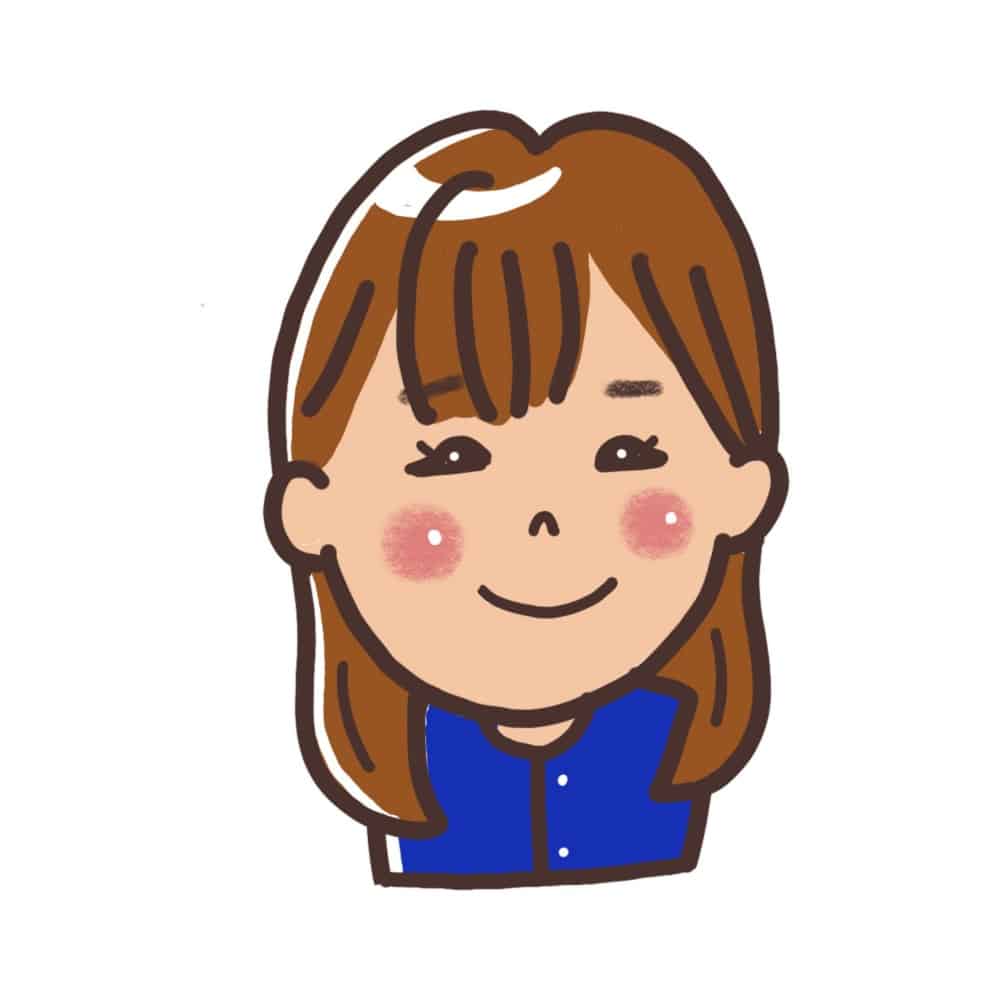





コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 触覚を使って遊ぼう […]
[…] 前回は、しっかり身体を使った遊びの紹介でしたが、身近にあるものを使った遊びもお伝えできればと思います。 […]