私は学校でこんなことに困った
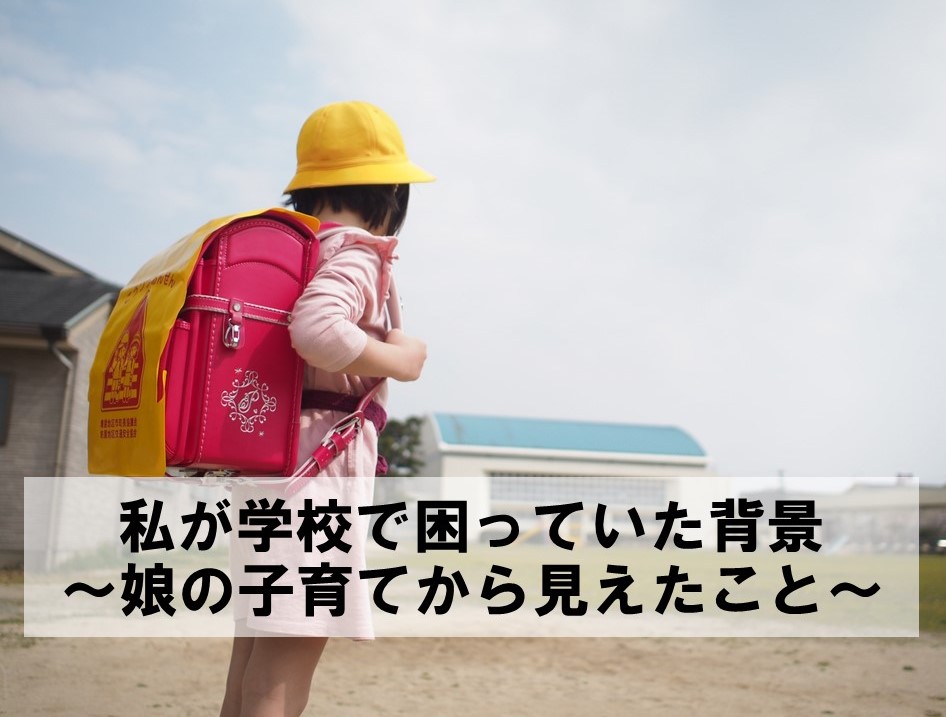
一年生のその後
娘は、コロナ禍の中、入学し、やっと2学期を終えようとしている。娘を見ていると、自分が一年生の時より随分勉強も安定してできていて、学校生活が楽しそうに見える。
私が入学する直前
前にも少し触れたが、私は、とても勉強が苦手だった。私は保育園の時、全く文字に興味を持たなかったらしく、母いわく入学式の前日に自分の名前のひらがなだけ教えたらしい。保育園で起きたことを母が迎えにきた頃にはすっかり忘れてしまい、いつも「Aちゃんと遊んだ」しか言わなかったらしい。
学校へ行くだけで
入学しても朝は、低血圧で早起きができず、朝ごはんもなんとか無理やり食パンを口に押し込んで飲みこみ、学校へ行っていた。重いランドセルを背負うだけでとても憂鬱で、やっと学校へ着いた頃にはヘトヘト。学校へ着いた頃やっとお腹がすく、そんな子どもだった。
姿勢もひどかった
そもそもそんな私の姿勢は、ぐにゃぐにゃだった。学校へ着いてすでにヘトヘトな私は、椅子へ座ってもだらっとしていて、「姿勢を正して」と言われた瞬間のみ、姿勢を正すことはできても、お辞儀をした後すぐに姿勢が崩れてしまっていた。また、頬杖をよくついていた。そうしないと重い頭を支えられなかった。高学年になると、椅子をキコキコ動かしていたのが、懐かしい。
居眠りも
当時は、保育園のお昼寝の名残りだと思っていたが、授業中によく居眠りをしていた。特に、給食を食べた後や体育のある日は、うとうとしていた。一年生の参観日の日も居眠りをしていたこともあるくらい、本当に毎日疲れていた。
なぜ疲れていたかというと
何で当時の私がそれほど疲れていたか、今振り返ると、登下校だけではなく、板書がとても苦手だった。黒板を見てノートに書き写す。そしてまた黒板を見た時に、次がどこだったか探すことが一苦労だった。これは教科書の文字をノートに書き写す時も同様で、一年生の放課後に居残りをして書き写しをさせられた経験もある。授業中にサボっていたわけではなく、真面目にやっていて、本当に時間内にできなかったのだ。
音読も苦手
教科書を読むのも、娘はさらりと読むが、私はすぐ助詞を飛ばしたり物語を勝手に作ってしまっていたと母が言っていたし、私の記憶の中でも、一文字ずつ指でなぞりながら、一音一音を読むような読み方しかできなかった。
家に帰ると
授業中ノートをとるのにも神経をすり減らし、もし音読で先生にあてられたらどうしよう。そんなことに神経を使い、しばらくは学校から帰ってからも昼寝をしていた。それでも宿題は必ずあったが、勉強が苦手な私は宿題にもとても時間がかかっていた。
娘がここまでスムーズなのは
なので、娘がこれほどまでにスムーズに学校生活を送れているのは、宇佐川研で教えてもらった取り組みを継続してきたおかげだと思っている。
勉強の代わりに家では…
私は、そんな学童期を過ごしたが、当時、父も母もフルタイムで働き、私が1年生の3学期頃、3人目の妹が生まれたこともあり、私の困り感に気を配る暇はなかった。
そのおかげか、1年生で家のことはある程度できた。簡単な食事は一人で作れたし、掃除、洗濯、お風呂洗い、ある程度の家事はこなせたし、妹の世話は大好きでよくやっていた。
勉強以外で娘はつまずいた
娘は、今のところ、勉強には困らなかったが、一年生の2学期の最初くらいまで、休み時間に誰と過ごせばよいかわからず、1人で絵を描いていたようだった。あんなに外遊びとお友達が大好きな我が子が、絵を描いて過ごすなんて信じられなかったが、担任の先生に尋ねると、その様子だと教えてくれた。
本人いわく、何人かのお友達を誘っても断られる経験が続いたり、体操服への着替えをするのに時間がかかり出遅れるので、後から運動場に出ても知ってるお友達を探せないと言っていた。
結局、担任の先生のアシストもあり、今では隣のクラスの子も混じって、男女関係なく、鬼ごっこをして過ごせるようになって、とても表情が明るく帰ってくるようになった。
忘れ物が多かった
また、一学期は忘れ物が多く、いろんな物を一つずつ忘れていたが、二学期に入ると、忘れ物を届けることがほとんどなくなったし、先生に言われた、図工に必要な材料も覚えて伝えてくれるようになった。
私は工夫や努力で苦手をサポート
私は相変わらず物覚えが悪いので、よくメモをとり、自分で自分をサポートしたり、夫とスケジュールを共有することで、忘れてはいけない予定があれば声をかけてもらうようにする等、工夫して生活している。
でももし、娘のような学童期が送れたら、きっとより円滑な学校生活が送れたと思うと、今困っている子どもたちに必要な支援ができる大人が一人でも増えてほしいと願ってやまない。
まみむめママ









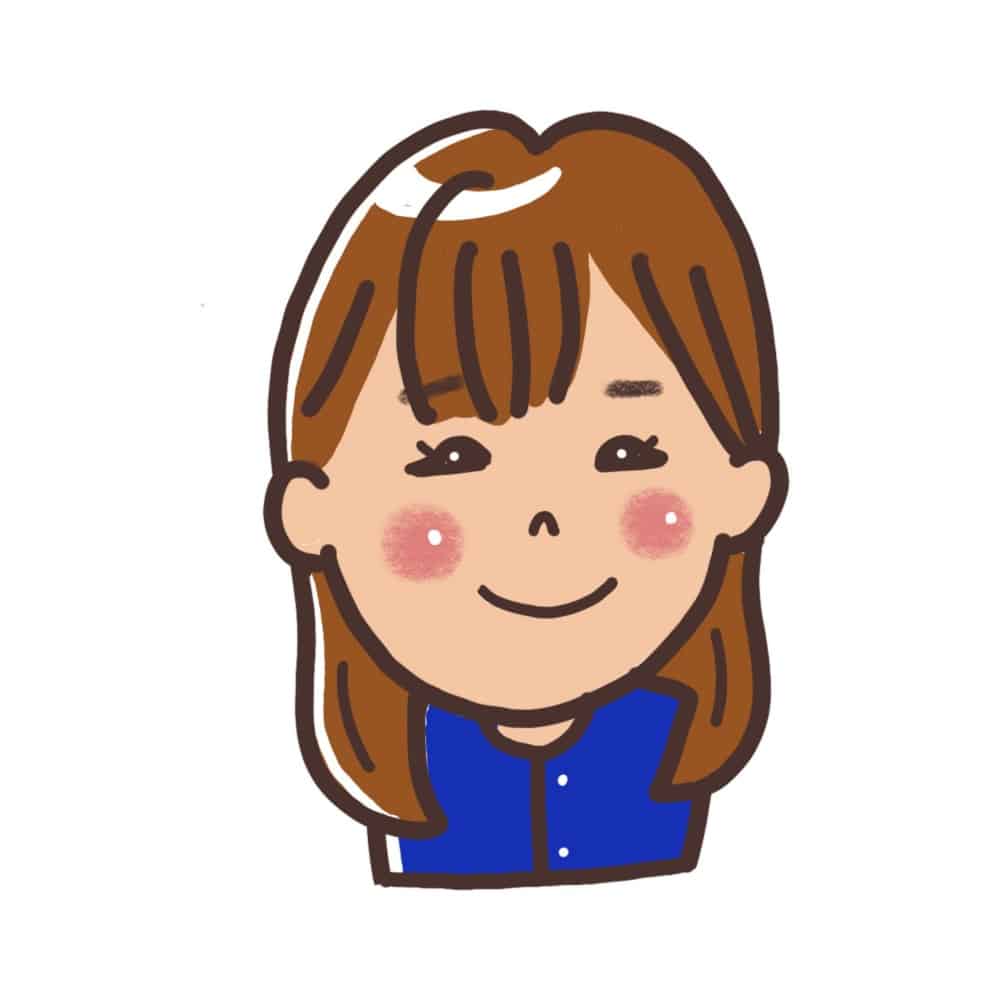




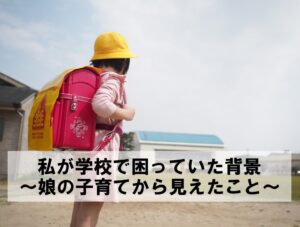
コメント