子どもの発達には遊び場を

上手く転ける(転がる)には
年末、5歳の娘と、小学校4年生の甥っ子とインラインスケートへ行きました。
宇佐川研で学んだ理論を取り入れて身体づくりをしてきた娘は、初めてのインラインスケートなので何度も転けますが(転がりますが)、1時間ほどで数メートル滑ることができるようになりました。
そこによく来ている方にも「上手だね」とビックリされるほど。私が見ていて感じたのは、娘は、転ぶのが上手だということです。手を前について転んだり、ひざも上手に使って転びます。
甥っ子は、普段外遊びをしないらしく、スケート自体も初めてでした。娘よりも体重や身長があるせいか、なかなか滑ることができません。手をついて転んだはずが、手を痛めてしまい、病院へ行くことになりました。
身体づくりをすれば
身体づくりと言っても、公園あそびや宇佐川研で教えてもらったバルンポリンしかしていません。でも身体づくりをしていると、公園で転けても顔を怪我することはほとんどありません。しかし、最近は、甥っ子のように自分の体重分を支えるだけの腕や体幹の力がなかったり、大切な頭を守るために反射的に手が前に出なかったりするお友達を目にします。
テレビやゲーム機、ゲームセンターでは、そんな当たり前の力が身につかないのです。
遊び場がなくなっている
最近では、公園に遊び場がなくなってきています。皆さんの近くの公園には、ブランコはありますか?撤去されたり、使用禁止になっている遊具がある公園が、増えてきています。私が子どもの時には、回転していたゆりかごの遊具も今はすべて固定されています。私が大好きだったくるくるまわるジャングルジムのような遊具も今では固定されています。そんな遊具でどう遊べというのでしょうか。
そもそも最近の子どもたちが、その遊具で遊ぶと怪我をするから撤去されるという図式です。回転に耐えられるだけ掴まれないから回転すると転落してしまうのでしょう。危険こそドキドキワクワクして魅力的だったりするのに、怪我をするから固定していけば、公園に魅力がもてないのも仕方がないように思います。
遊具だけではありません。公園でボール遊びはできますか?禁止事項はたくさんありませんか?子どもは、その公園で何をして遊ぶのでしょうか?
昔は遊びの中で無意識に自分の必要な刺激を好きな時に好きなだけ自分で取り入れることができていました。
子どもたちの発達を促進するためにも、公園のあり方が変わればいいなと思っています。
でも、待っているだけでは子どもたちの大切な時間はどんどん過ぎ去っていってしまうだけですので、日々の遊びの中に家庭でできることや、近所でできることを取り入れていきたいと思います。
そのためにも、楽しいことはもちろんのこと、今だからこそ必要な発達課題を意識しながら取り組めたらと思います。
宇佐川研で教わった「基礎感覚」の知識は、正に子どもたちの育ちの大きな基礎を築いてくれるんだなぁって、年数がたつにつれて強く感じます。
まみむめママ









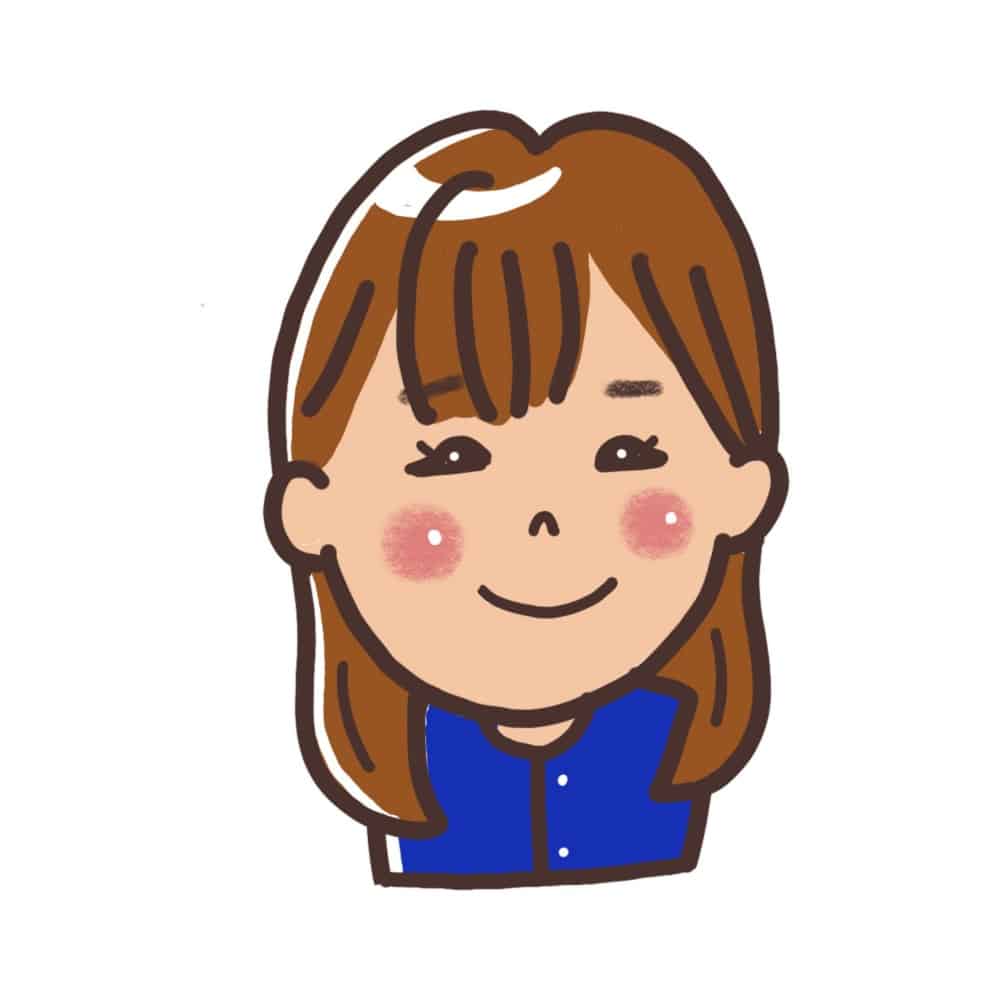





コメント