まるごと我が子を受けとめよう
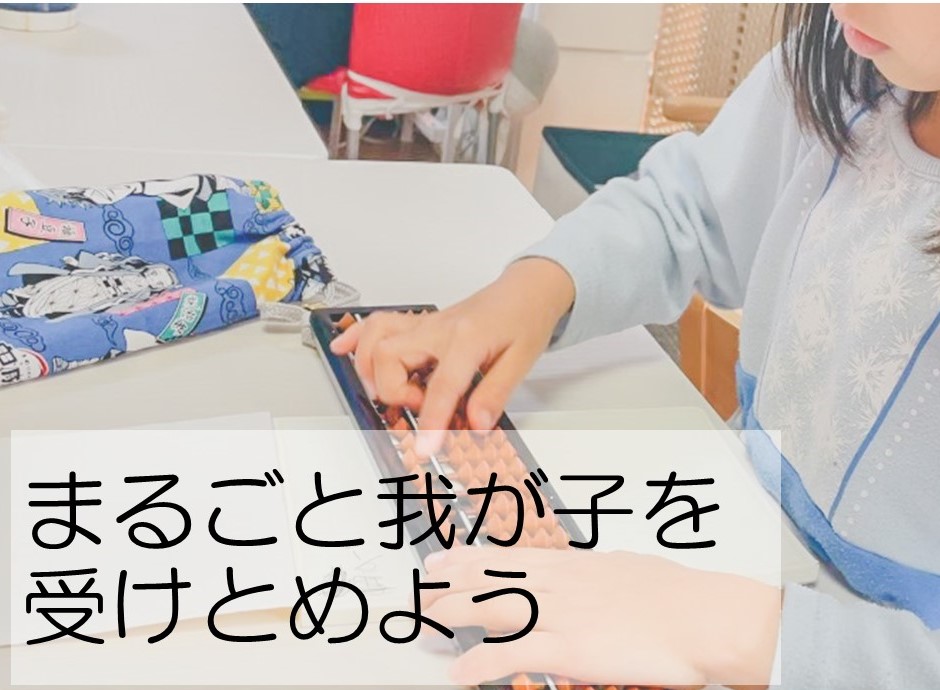
そろばんを習い始めたらWiscでも変化が
年長にもかかわらず、あまりにも商売っ気のある娘なので、2020年11月からそろばんを習い始めました。その甲斐もあってか、WISCの試験中に面白いことがありました。
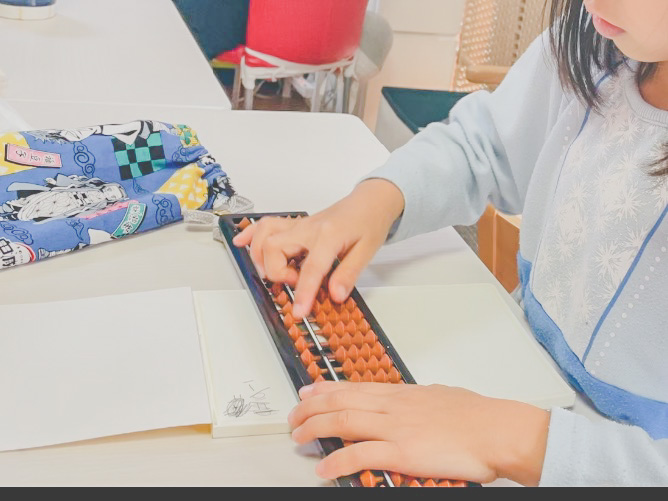
娘は意外と算数が得意だった
私は、娘が受けている後ろで娘の様子を観察していると、先生から算数のような問題を口頭で言われて、それについて答えるテストがありました。
例えば、「公園で3人遊んでいます。1人帰りました。今、公園には何人いますか?」といった具合です。
その問題に、あまりにも娘が答えられるので、驚きました。
人が好きな長所が底上げ?!
特に面白いのが、娘の答えられる問題は、「人」が携わる問題だったことです。誰かが食べたとか、誰かが公園に来た後、数名が帰ったという問題をすらすら答えるのです。


休みの日の度に「お友達と遊びたい」と嘆いているだけあり、人が好きなことが功を奏して、この問題が得意でした。
植竹先生の見解
私は、このエピソードを宇佐川研の植竹先生に伝えずにはいられませんでした。
このエピソードを伝えると、植竹先生から「象徴機能がググンと伸びてきているんですね。そろばんは効果がありそうですね。あとは、ベースとなる基礎感覚をしっかりと育ててきているからでしょうね。あと、元々頭の回転は速いので、持ち前の力を発揮していると思います。
人が好きというのも当てはまると思います。
「頭の中にイメージが湧きやすいんでしょうね。」とお返事をいただきました。
以前から耳から聞いた情報を処理する力の方が得意で、処理速度が長けていたので、そこにそろばんが加わったことで、頭の中でイメージする力ができるようになったことで、成長を感じたのだと思います。
得意なことを伸ばそう
そこで初めて気づいたことがあります。それは、私は今まで娘の苦手なことを必死に伸ばそうとしていました。しかし、最近は、苦手なことよりも得意なことをいかに伸ばすかを無意識のうちにやっていたのかもしれません。
私が娘のまるごとを受け止められるようになってきたから、先日も「苦手なことだってあるよ。ママも今だって苦手なことあるし。苦手なことがあっで生きていける。大丈夫、大丈夫。」と娘に声をかけました。
実は私、、、
私は、自分が子どもの時は振り返ると、今でいう学習障害があったように思います。
母から聞いた話だと私は、入学式前日まで全く文字にも数字にも興味を持たなかったらしく、入学式前日に母が私の名前のひらがなだけ教えたそうです。
他にも、授業時間内に黒板や教科書をノートに書き写せず、一年生で居残りをさせられたことがありました。
音読も苦手で、一行とばして読んだり、助詞を勝手に変えて読むので、私が音読の宿題をする時、母は教科書から目が離せなかったそうです。
なので娘の子育てをしていると、年長でこんなにもいろんなことができるんだと驚きの連続です。
でも私がそんな小学校生活を送っていても、大学にも行き、就職もし、家族もいる。今困っていることは、物覚えが悪いことかな。それもたくさんメモをとることで補っています。
どんな自分も娘もまるごと受け止める!

そんな現実を自分がまず、受け止められるようになったからこそ、娘にも苦手があったっていい。できないことが一つ、二つあったっていい。大好きな娘を得意なことも苦手なことも含めて、まるごと受け止められるようになりました。
本当は、娘が生きていてくれること、それだけですべて花丸。
まみむめママ









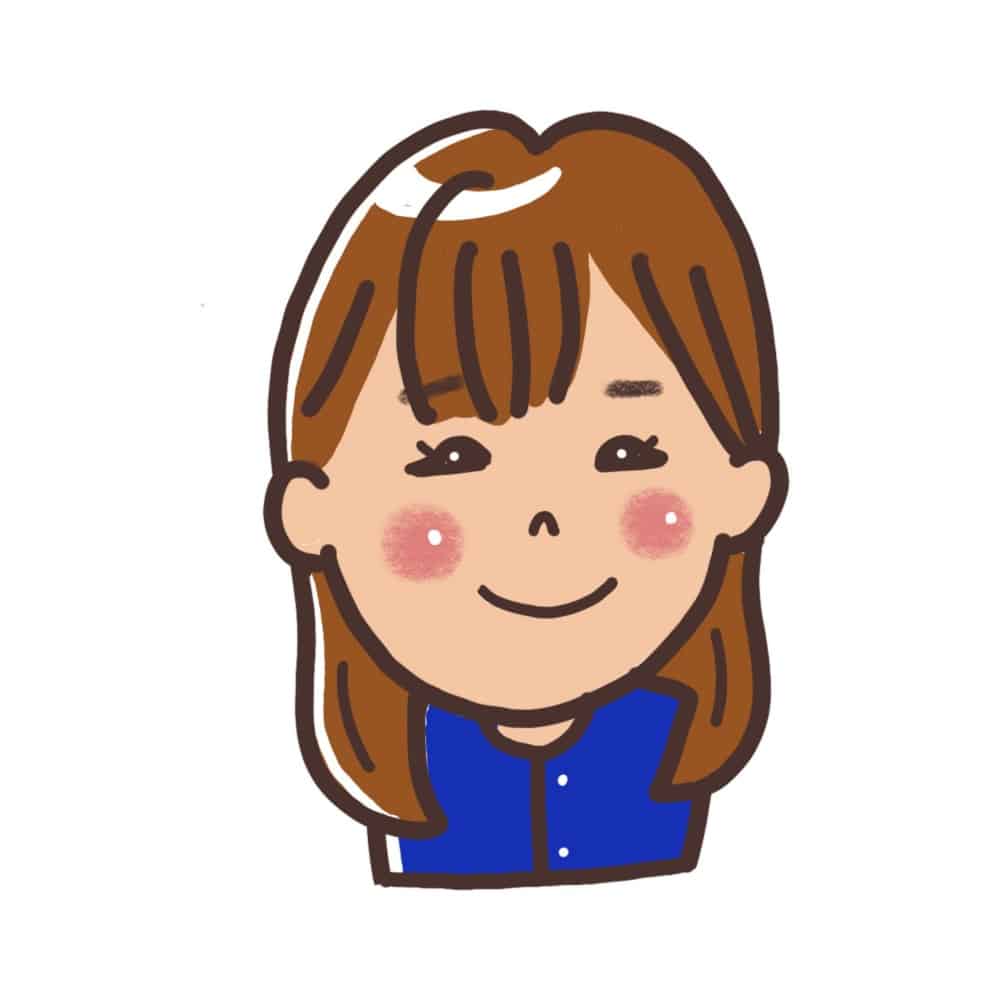




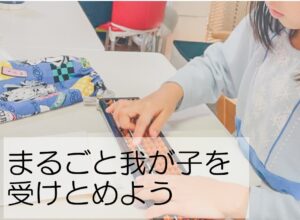
コメント