赤ちゃんが叫ぶように泣くのはなぜ?
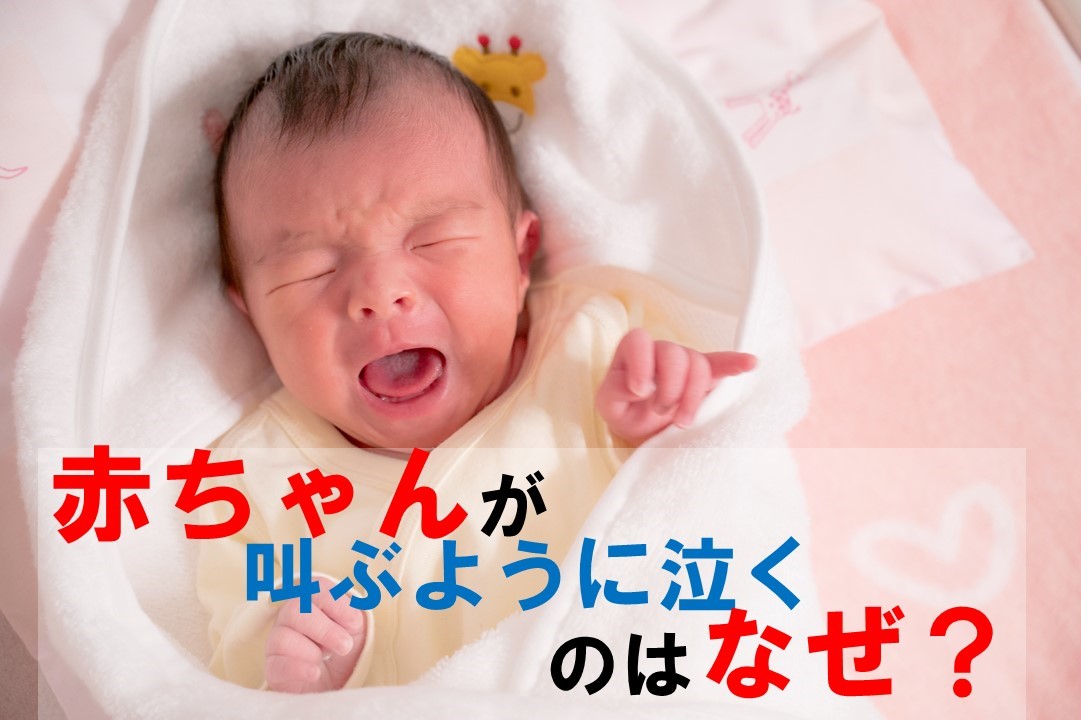
赤ちゃんは突然火がついたように泣くことがあります。あまりの激しい泣き方に「え、大丈夫なのかしら」と心配になってしまうパパやママもいらっしゃるかもしれません。
奇声のような泣き方が続いてしまうとママも精神的に参ってしまいますよね。そこでここでは赤ちゃんが叫ぶように泣く時の理由や対処法について考えてみました。
今まで赤ちゃんの奇声や叫ぶような泣きに悩まされていた方の参考になればと思います。
赤ちゃんが叫ぶように泣く、その理由や対処法について
理由1:自分に注目してほしい
赤ちゃんからするとママの存在というのはとても大きいです。
大好きなママの注目を集めたい、そんな時も激しく泣いてしまうことがあります。ママの方を向いて奇声を上げる。そんな時はママに遊んでもらいたいと思っている可能性が大です。
対処法としては、赤ちゃんと一緒に遊ぶ時間を作ってあげると良いですね。。とは言っても家事など、やらなけれはいけない事がママにはいっぱいありますよね。
ただ、赤ちゃんからするとそんなことはお構いなしです。
なので、可能であれば少しの時間でも良いので一緒に遊んであげれると良いですよね。そうすることで、赤ちゃん自身も満足して大人しくなるかもしれません。
理由2:眠い、疲れた
赤ちゃんが夕方に突然、けたたましい声で泣き叫ぶ事があります。
一般的に”黄昏泣き(たそがれなき)”などとも言われていますが、この”黄昏泣き”は、1日の疲れが一気に出てくる夕方頃が多いです。
これは疲れによって赤ちゃん自身が感情をコントロールする事ができないからとも言われています。
対処法としては、周囲が暗くなる夕方頃になったら部屋の明かりをつけて明るくしてあげたり、抱っこして「今日はいっぱいがんばったね」などと話しかけてあげたりするのもおすすめです。
その他にも、大好きな歌を歌ってあげたりすると赤ちゃんの気分が落ち着くこともあります。
理由3:不安や戸惑いを感じている
赤ちゃんにとっては毎日が新鮮で新しいことばかりです。なので、場合によっては不安になったり戸惑ってしまうこともあります。
例えば、
・初めて車に乗ったり
・初めて電車に乗ったり
・初めて友人知人のお家に行った時
など、赤ちゃんからすると不安になってしまうことだらけかもしれません。
そんな時の対処法としては、
・抱っこして優しく笑顔で話しかけてあげたり
・頭を撫でてあげたり
とにかく大丈夫なんだよ。という事を伝えてあげると良いですね。
特に抱っこに関してはママの体温や鼓動などを聞いているうちに赤ちゃんも徐々に安心してくることが多いです。
理由4:体調不良
赤ちゃんは自分自身で体調管理ができません。
自分の体調を泣いてしか知らせる事ができない場合もあります。いつもと違う奇声を発したり、なんだか様子がおかしい場合は速やかに病院を受診するようにしましょう。
パープルクライングの可能性
パープルクライングというのは生後2週間頃から生後5ヶ月くらいまで続く”理解困難な泣き”を指しています。
もちろん個人差はありますが基本的には健康な赤ちゃんのよく泣く時期を指しています。
ちなみにパープルクライングのパープル(PURPLE)は以下のような赤ちゃんの泣き方の特徴の頭文字を取ってできた造語になります。
P:Peak of cring・・・ピークがある(生後2~3ヶ月がピーク)
U:Unexpected・・・明確な理由もなく予測すらできない
R:Resist to soothe・・・なだめても泣き止まない
P:Pain like face・・・痛くないはずなのに痛そうな顔をして泣く
L:Long lasting・・・長時間泣き続ける(5時間以上泣くことも、、)
E:Evening・・・夕方から夜にかけて泣きが集中する事がある
参照:https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/material/files/group/109/naki.pdf
こういった言葉もありますのでパープルクライングの可能性も考えておくと案外気持ちも楽になるかもしれませんね。
泣き止まない赤ちゃんに対して絶対にしてはいけない対処法
赤ちゃんがなかなか泣き止まない、そんな時もあります。しかし、イライラしてしまって乱暴な接し方だけはしないようにしましょう。
例えば、泣き止ませたいがために激しく揺さぶったりしてしまうと、脳に損傷を与えてしまうだけでなく、場合によっては最悪、死に至るケースもあります。
相手が赤ちゃんである事を決して忘れずに接する事が大切です。
まとめ
今回は赤ちゃんが叫ぶように泣く、その理由などについて考えてみました。
昔から”赤ちゃんは泣くのが仕事”などとも言われたりしますが、分かってはいても参ってしまうこともあります。
ずっと激しく泣いている赤ちゃんに対してイラッとしてつい叱ってしまいがちになるかもしれません。
しかし、自分も昔は同じだった。このように思うことで赤ちゃんに対する考え方も少しは変わるのではないでしょうか。















コメント